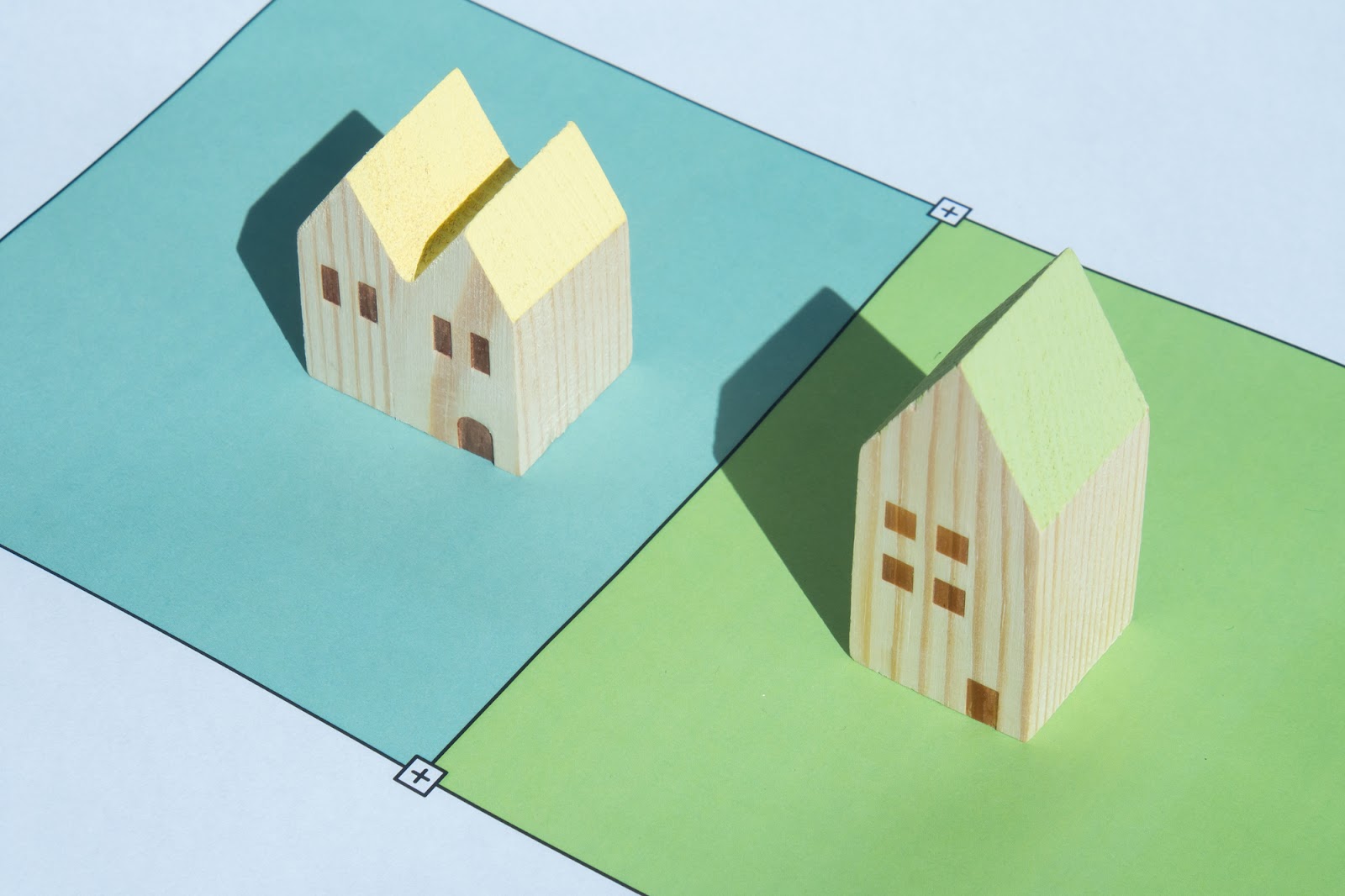公図は、不動産・山林取引において土地の区画や形状、地番といった情報を公的に証明する重要な役割を担っています。
今回は、公図の見方や取得方法について、詳しく解説していきます。不動産・山林取引をスムーズに進めるためにも公図に関する知識を深めましょう。
この記事の目次
公図とは何か?
不動産・山林売買や境界確認の際に「公図」という言葉を耳にすることがあるでしょう。公図とは、法務局(登記所)が管理している地図のことです。土地の区画や形状、地番といった情報を公的に証明する重要な役割を担っています。
公図は、不動産登記法という法律に基づいて作成されており、土地の所有権や抵当権などの権利関係を明確にするために欠かせない情報が記載されています。
具体的には、以下のような情報が公図に記載されています。
地番:土地ごとに割り振られた番号で、土地を特定するための重要な情報です。
境界線:隣接地との境界を示す線で、実線や破線で表現されます。
道路:公道や私道など、道路の種類や幅員が記載されています。
水路:河川や用水路など、水路の種類や幅員が記載されています。
公図は、これらの情報を基に、土地の形状や区画、隣接地との関係などを把握することができます。
不動産取引や境界確認だけでなく、建築確認申請や相続手続きなど、不動産に関する様々な場面で活用される重要な資料であると言えるでしょう。
公図は2種類に分けられる
公図は、その作成方法や精度によって、以下の2種類に分けられます。
地図(不動産登記法第14条地図)
不動産登記法第14条第1項に規定されている図面のことで、地籍調査に基づいて作成され、土地の形状や境界が正確に表現されています。
縮尺は地域によって異なり、都市部では1/500や1/1000、郊外では1/2500などが一般的です。境界線を復元できる精度を持ち、土地の面積や距離、形状、位置について信頼性が高い情報源となります。
地図に準ずる図面
測量ではなく、土地の分筆や合筆などの登記手続きの際に作成された図面を基に作成されたものです。地図に比べて正確性は劣りますが、土地の区画や地番などの基本的な情報は得られます。
地図に準ずる図面は、明治時代の地租改正時に作成されたものが多く、地図が作成されるまでの代わりの図面として法務局に備え付けられています。
地図が完成すると取り替えられるため、1つの土地に「地図」と「地図に準ずる図面」の両方が存在することはありません。
公図は、厳密には「地図に準ずる図面」のことですが、地図と併せて「公図」と呼ばれるのが一般的です。
公図の見方
公図には、土地に関する様々な情報が記載されています。
公図に記載されている主な情報
公図の上部図面の箇所には、土地の区画や地番が記載されています。
図面の下には、地図に関する情報が記載されています。具体的な項目は以下のとおりです。
- 所在
- 地番
- 出力縮尺
- 精度区分
- 座標系番号または記号
- 分類
- 種類
- 作成年月日
- 備付年月日
- 補記事項
分類には「地図(法第14条第1項)」もしくは「地図に準ずる図面」、種類の欄には「法務局作成地図」「地積図」などと記載されます。
公図を見る際のポイント
縮尺を確認する
公図は縮尺によって表示される範囲や情報量が異なります。縮尺を確認し、必要な情報が記載されているかを確認しましょう。
地番を確認する
目的の土地の地番を確認し、その土地が公図のどこに表示されているかを確認しましょう。
境界線を確認する
隣接する土地との境界線を注意深く確認し、境界が確定しているか、未確定であるかを確認しましょう。
周辺の状況を確認する
道路や水路、建物などの周辺の状況を確認し、土地の利用状況や環境を把握しましょう。なお、地番のない道路は「赤道(赤地)」、河川や水路部に該当する土地は「青道(青地)」と呼ばれます。
公図の取得方法
公図は、以下に挙げる方法で取得できます。
法務局の窓口で申請する
管轄の法務局に直接出向き、窓口で「地図の写し」を請求する方法です。土地の所在する場所を管轄する法務局であれば、全国どこの法務局でも請求できます。
インターネットからPDFファイルでダウンロードする
法務省が運営する「登記情報提供サービス」を利用すれば、インターネットから公図のファイルをダウンロードできます。
ただし、法務局から入手する場合と違い、証明文や公印など公的な証明はありませんのでご注意ください。
「ただ閲覧したい」という方に向いている方法であり、利用前には登録手続きを行う必要があります。
法務局へのオンライン申請をする
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、オンラインで公図の交付を申請できます。申請後、法務局の窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選択できます。
正式に発行された公図であることを証明する必要がある場合でも、登記所に出向かず、自宅や勤務先などから申請することが可能です。
郵送で取り寄せる
管轄の法務局に郵送で公図の交付を請求することも可能です。法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して郵送します。
公図の取得にかかる手数料(1通あたり)
- 法務局の窓口で受け取る場合:450円
- 「登記情報提供サービス」を利用する場合:361円(令和6年4月1日時点)
- 「登記・供託オンライン申請システム」を利用して窓口で受け取る場合:430円
- 「登記・供託オンライン申請システム」を利用して郵送で受け取る場合:450円
- 郵送で取り寄せる場合:450円
まとめ
今回は、不動産・山林取引や境界確認に欠かせない「公図」について、基本的な知識から取得方法まで解説しました。
公図は、土地の所有権や境界などを明確にするための重要な公的資料です。不動産・山林売買や境界確認、建築確認申請など、様々な場面で活用できます。法務局の窓口やインターネット、郵送など、様々な方法で取得できます。
公図を確認し、不動産・山林取引や境界確認を行うことは、土地や山林に関するトラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を実現することができます。